みなさんの会社では、オフィス備品を適切に管理していますか?
オフィスの備品管理は、煩雑で面倒な業務ですが、しっかり体制を調えて組織的に実施しなければ、 不正会計や放漫経営、離職率の高止まりなど、 経営上のあらゆるリスクを高めることになります。
本記事では、備品管理の方法・実施手順、効率よく実施するコツ、注意点、効率化ツールなどについて解説します。
会社の備品管理に携わる人は、ここで紹介する内容に沿って、会社の備品管理体制を整えてみてください。
目次
はじめに、「備品管理」関連記事の中で、特にアクセス数の多い6つの記事を「備品管理の基礎知識まとめ」として紹介します。参考にしてみてください。
備品管理の基礎知識まとめ
【備品管理台帳(備品管理表)】エクセルテンプレート&作成方法まとめ
備品管理台帳(備品管理表)の作成方法、項目例などについて解説しています。エクセルテンプレートもダウンロード可能です。
【備品管理ラベル・シール】使い方・作成方法・Q&Aまとめ【サンプル画像あり】
備品管理ラベル(シール)の作成方法、貼り方、貼れない場合の対処法などについて解説しています。
【備品管理システム】導入前に押さえるべきポイント・使い方・導入事例
備品管理システムでできること、導入を検討する場合の注意点、導入事例などについて解説しています。
【備品管理アプリ】選び方・使い方・機能・できること
備品管理に使えるスマホアプリについて、使い方や機能などとともに紹介します。
【備品管理の改善方法】改善アイデア5選。精度・効率を改善する方法とは?
備品管理の作業効率や正確性を改善する5つのアイデアを紹介しています。
【備品の持ち出し管理】管理方法&注意点を確認しよう
会社の備品の持ち出し・貸出しを手軽に管理する方法と注意点について解説しています。
また、以下で、備品管理の目的と必要性、業務フロー・作業手順、押さえるべきポイントや注意点などについて解説します。
【大変だった備品管理をスマホ&QRコードで半自動化!!】
物品管理システム「Convi.BASE(コンビベース)」を使って作業工数を1/10に圧縮!
- ブラウザ&スマホで操作が完結。リモートでも管理できる
- カスタマイズ自由&枚数追加可能なクラウド台帳
- QRコードのスキャンで「貸出し・返却管理」「入出庫管理」「在庫数量管理」「棚卸し」
- 管理画面からボタン1つでQRコード発行・印刷
- 任意の条件でアラートメール送信
- アカウント単位でアクセス権限設定
⇒ Convi.BASE(コンビベース)の詳細資料を見てみる
備品管理とは?
備品管理とは、企業などの組織において、いわゆる「オフィス備品」の保管場所や使用状況、使用者、状態などの情報をデータベース化し、ルールに則って取り扱う一連の仕組みのことをいいます。
備品管理により得られる5つのメリット
企業などの組織が備品管理を実施する理由は、備品管理を行うことでさまざまなメリットを得られるからにほかなりません。では、備品管理にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
備品管理により得られるメリットは主に次の5つです。
備品管理の5つのメリット
ひとつずつ解説していきます。
1. セキュリティ担保
第一に、セキュリティを担保できるというメリットがあります。
ほとんどの企業は、万が一、流出や破損させてしまった場合、会社または他の第三者に経済的・社会的な損害を与える可能性のある物品を扱っているものです。たとえば、大量の機密情報や顧客情報を含むデータが保存されているサーバールームの鍵、人体や環境に有害な廃棄物、さまざまなクラウドサービスのログインID・パスワードが保存されているPC……。
このような備品が、社員一人の一存で簡単に持ち出すことができる状態に置かれていれば、万が一、社外に流出し不正に利用されたとしても、すぐに気づくことができません。顧客や取引先の生命・財産を脅かすような大事件に発展する危険性もあります。
備品管理は、こうしたセキュリティ上のリスクを排除し、従業員の生活や社会の秩序を守るために必要なのです。
2. 不正防止・透明性確保
第二に、従業員や経営陣による不正を防げるというメリットがあります。
備品は、事業の用に供すべき会社の資産であり、事業のために活用されなければいけません。しかし、もし適切な備品管理をしていなければ、購入した備品が実際に事業に使われていることを証明できなくなってしまいます。たとえば、従業員が私用するつもりのものを「業務で使うため」と偽って経費で購入したとしても、会社は把握できないでしょう。あるいは、社長が株主や従業員に分からないように、会社の資金を事業と関係ない自分の趣味に使い込む、ということもできてしまいます。
備品管理は、こうした会社の私物化や横領などの不正を防止し、購入した資産物品がどのように活用されているかを、社内外のステークホルダーに示すために必要なのです。
3. 生産性向上
第三に、備品の保管場所や使用状況を誰でも瞬時に確認できるようになることで、組織の生産性が向上する、というメリットがあります。
たとえば、社内に保管されている物品の中から必要な備品を探し出す作業は、時に非常に時間がかかります。特に、備品の数が多かったり、部屋・フロア・事業拠点が複数あったりする場合、探している本人が考えている以上にチーム全体の生産性を低下させることになります。また、使用する予定でいた備品を他の誰かが使っていて、すぐに使用できない、という場合には、業務の進捗に遅れをきたすこともあります。
このような非効率を無くし、より生産的な活動に集中できるようにするためにも、備品管理が役に立ちます。
4. 経費削減・節税
第四に、備品の利用状況が可視化されることにより、無駄な経費を削減したり税金を抑えたりできる、というメリットがあります。
備品管理の仕組みが上手く機能していると、たとえば、新入社員用にPCを用意する際、他部署に未使用のPCが何台残っているかすぐに分かるので、余計に買い足すことなく遊休品を有効活用できるようになります。
また、「足りてない備品」「使われていない備品」「壊れている備品」「現場の判断で処分された備品」などを誰もが確認できるようになるので、たとえば会社の業績を踏まえて購入数や購入時期を調整したり、素早く除却処理を行ったりして、賢く税金を圧縮することも可能になります。
5. 従業員満足度の向上
第五に、従業員満足度が向上する、というメリットがあります。
適切な備品管理の体制ができていないと、会社は横領や不正会計、放漫経営が発生しやすい状態に陥ります。セキュリティ対策も不十分になるので、個人情報流出などの不祥事が起こるリスクも高くなるでしょう。こうなると、従業員に努力して働こうというインセンティブが働きにくくなり、優秀な社員ほど社を離れていくようになります。
備品管理は、組織を健全に保ち、従業員が満足度高く働ける環境をつくるためにも必要なのです。
備品管理を始めるタイミングは?

現時点で備品管理の仕組みが整っていない、という企業もあるでしょう。そのような企業の場合、いつ備品管理を始めるべきでしょうか。
結論から言うと、可能な限り早く体制整備に着手すべきです。
なぜなら、後になればなるほど、初動の体制整備にかかる負担が大きくなるからです。一般的に、時間が経てば経つほど、企業は成長し、事業拠点・部門・従業員・備品などの数は増えていくものです。
ですから、できるだけ組織規模が小さく、管理すべき備品や保管場所の数が少ないうちに、管理の仕組みを整えておいた方が効率がよいのです。実際、従業員数十人程度までの組織規模であれば、ものの数時間程度で基本的な備品管理の仕組みを整えることができます。
一方で、既にある程度組織規模が大きくなっているのに、備品管理の仕組みが整っていないという企業も存在します。この場合、初動の体制整備にはかなりの時間と労力がかかるため、管理体制の構築に二の足を踏んでしまっている担当者も多いのではないでしょうか。
そういう企業の場合、オフィス移転やレイアウト変更などのタイミングで管理体制の整備に着手すると良いでしょう。
また、手始めに総務部門など備品管理を管轄する部門のみで管理体制を確立し、その後で順次他部門や他拠点をその管理体制に巻き込んでいく、という手法も有効になります。
備品管理の始め方。5つのステップ&用意するもの
では、 実際に備品管理を始める時にはどのような手順で進めればよいのでしょうか。5つのステップに分けて紹介します。
【備品管理のやり方・始め方】5ステップ&用意するもの
1. 備品の現状把握を行う
まずは、組織が保有するすべての備品の棚卸しを行います。不要な備品・使用されていない備品があれば、処分・売却します。
2. 使用シーン別に分類する
次に、「共有すべき備品はキャビネット」、「日常的に使う備品は各自のデスクの上」、「日頃使わない備品は保管室」など、備品を使用シーン別に分類します。
3. 備品管理台帳を作成する
備品管理台帳を作成し、備品の所在・管理部署・個数などを記載していきます。備品管理台帳はクラウド上に保存し、いつでもどこでも確認・更新ができる状態にしておくと良いでしょう。
備品管理台帳の作成方法については下記のページで詳しく紹介しています。エクセルテンプレートも無料ダウンロードできるので参考にしてみてください。
台帳作成後は、定期的なチェック・更新に加え、備品の購入や廃棄の都度、忘れずに入力するようルールを定めておきましょう。
4. ラベリングする
消耗品は総務部、デジタル機器は情報システム部など、すべての備品に購入年月日や管理部門(部署)を記載したラベルを貼り、備品管理の責任の所在を明確化します。
備品管理ラベルの作成例や貼り方、貼れない場合の対処法などについては下記の記事で詳しく解説しています。参考にしてみてください。
5. 管理ルールを作る
管理ラベルの貼付や台帳への記載ができたら、「使用前に承認印をもらう」「指定した時間に返却する」などのルールを整備してください。ルールはマニュアルとして文書などにまとめておくと共有しやすくなります。
備品の管理体制が整っていない組織の方は、まずはここで紹介した手順に沿って、最低限の管理体制を構築することからはじめてみてください。
備品管理の方法は? 運用フェーズの業務フロー&作業手順4パターン
備品管理の体制を整え、管理をスタートさせた後は、次の事象が発生する度に、手順に従い業務を進めていきます。
【備品管理の方法】運用フェーズの業務フロー&作業手順
パターン① 新たに備品を購入するとき
新たに備品を購入する場合は、以下の流れで対応します。
| 1. 事前検討 | 資料請求、見積りの取得などにより、最適な製品、最適な取得形態(購入/リース)を決定する |
| 2. 発注 | 見積りや稟議を通して職務権限規程上の決裁者に承認を得た上で発注する |
| 3. 検収 | 発注書、納品書、現物を照合し、不備・不良、品質・性能の相違などが無いか検品を行う。契約書、保証書、マニュアルなどの重要書類を規程に従い保管する |
| 4. 台帳登録 | 名称、管理部門、保管場所、取得価額など、管理に必要な情報を固定資産管理台帳に登録する |
| 5. ラベル貼付 | 備品管理番号を記したラベル(シール)を発行し、備品に貼付する |
パターン② 備品を故障・破損・紛失したとき
稼働している備品を故障・破損・紛失したときは、以下の流れで対応します。
| 1. 保証・保険の確認 | 備品の状態を踏まえ、適用できる保証や保険が無いか確認する |
| 2. 対応方法検討 | 修繕する場合と再購入する場合のコストを比較し、最適な対処法を決める |
| 3. 発注 | 修繕または再購入の発注を行う。現在保険が付与されておらず、保険を付けた方が維持コストを下げられる場合は、保険加入手続きを行う |
| 4. 台帳更新 | 状況に合わせて「修繕中」「廃棄」「紛失」など備品管理台帳の記載内容を変更する |
パターン③ 備品が不要になったとき
稼働している備品が不要になったときは、以下の流れで対応します。
| 1. 対応方法検討 | 今後(他部門も含め)自社で使用する可能性がある備品の場合は「遊休品」として別途保管する。自社で使用する可能性がない備品の場合、「売却」と「廃棄」のどちらで処理するか決める |
| 2. 遊休/売却/廃棄の実施 | 「遊休品」とする場合、所定の遊休品保管場所に備品を移動させる。「売却」「廃棄」の場合、法令や社内規程に則り最適な方法で売却や廃棄手続きを進める |
| 3. 台帳更新 | 状況に合わせて「修繕中」「廃棄」「紛失」など備品管理台帳の記載内容を変更する |
パターン④ 備品の定期棚卸し(現物確認)
定期的に備品の保管場所に行き、備品の状態を確認しましょう。そうすることで、台帳の更新漏れや入力ミス、誰にも気付かれないまま故障していた備品の情報などを正確に把握し、台帳の記載内容を、実態に即した内容に修正することができます。
年1~2回の頻度で実施している企業が多くなっています。

備品管理の注意点は? 押さえるべき4つのポイント&コツ
ここからは、備品管理をスムーズに軌道に乗せるために押さえておくべき次の4つのポイントと注意点、運用のコツについて紹介します。
【備品管理の注意点】4つのポイント&コツ
ポイント① 管理を行う目的が明確になっているか
最初に、管理を行う目的が明確になっているか確認してみてください。
コンサルティングを行っていると、時おり、目的が曖昧な状態で備品管理に取り組んでいる状況を目にすることがあります。明確な目的なく行う備品管理は、中身のない形だけのものになってしまいます。社員の時間をただ奪うだけで、本来なら得られるはずのメリットも得られません。管理体制を整えようにも、どの範囲までの備品を、誰が、どのような方法で管理すべきか判断すらできないはずです。
「前任者がやっていたので」「上に言われたので」
このようなきっかけから備品管理に取り組んでいるという人は、なぜ備品管理を行う必要があるのか、先述の「備品管理の5つのメリット」などを参考に、改めて定義してみてください。
目的が複数ある場合は、優先順位をつけて3〜5つ程度に絞ると、その後の仕組みづくりがやりやすくなります。
ポイント② 管理対象が明確になっているか
次に、管理対象とする備品の範囲が明確になっているか確認してみてください。
ポイント①で定義した「管理の目的」を達成するためには、どの備品を管理対象とすべきか、という観点で定めるようにしましょう。管理対象に含まれるかどうか誰でも判断できるよう、明確な基準を設けることが重要です。たとえば、次のような具合です。
- 取得価額が5万円以上の物品
- 管理部・営業部・開発部が管理する物品
- 自社管理物件の鍵
管理対象は、必要以上に広げないよう注意してください。管理目的・管理対象を絞り込んで明確化した方が、管理のメリットを得やすくなります。
ポイント③ 管理する人が明確になっているか
管理する人を明確化することも重要なポイントです。
備品ごとに「管理する人」すなわち、「管理担当者」を定めていない場合、管理の過程で必要になるさまざまな作業が、備品管理業務の責任者に一挙に集中してしまうことがあります。
管理作業のすべてを責任者が行うのは現実的ではありません。むしろ、多くの作業は、実際に備品を扱う現場でやった方が効率がよいはずです。備品ごとに、その備品の管理に責任を持つ担当者を定めるようにしましょう。担当者は一定のルールに基づいて機械的に決められるよう明文化しておくことが重要です。たとえば、次のような具合です。
- 備品の発注作業を行った人を管理担当者とする
- 備品購入の決済作業を行った人を管理担当者とする
- 備品取得の決裁権者を管理担当者とする
- 備品の保管部門の責任者を管理担当者とする
- 各部門1名ずつ指名した備品管理担当者を管理担当者とする
ポイント④ 管理フローに従って処理されているか
最後に、実際に現場社員が、管理規程やマニュアルで定めた管理フローに従って備品を取り扱えているか、チェックしてみてください。
チェックには、定期棚卸しの結果を用います。棚卸し結果の照合率が100%に近いほど、マニュアル通りの取り扱いができているということになります。棚卸し結果と台帳の記載内容に、記入ミス・確認ミス以上の差異がある場合は、ルールの浸透が不十分である(またはルール自体に欠陥がある)ことを疑ってよいでしょう。
台帳や管理規程を作成したところで、それが現場で正しく活用されなければ、本来のメリットは得ることができません。極力、差異が出ないよう、現場と協力して管理規程やマニュアルをブラッシュアップしていくことが重要になります。
備品管理を効率化する方法は?
ここまで読んでいただいた方には理解いただけたと思うのですが、備品管理は手間と時間がかかる作業です。どうにか効率化したいと考えている担当者も多いのではないでしょうか。
そのポイントは、複雑な作業なく、誰でも簡単に実施できる仕組みを作ることです。
しかし、その仕組みを一から組み立てるのは容易ではありません。
ここからは、その仕組みを簡単に構築し、手早く効率的に備品管理を始める2つの方法と、その注意点について解説していきます。
備品管理の効率を改善する2つのツール
備品管理システムの導入
効率的な備品管理の仕組みを手早く構築する手段のひとつに、管理システムの導入が挙げられます。
現在、備品管理に使えるシステムはいくつか存在しますが、各製品、使い方や機能は大きく異なるため、どうやって絞り込めばよいか分からず困っているという人も多いのではないでしょうか。
そんな人には、「スキャンで管理できるかどうか」という基準で候補を絞り込んでみることをおすすめします。
なぜなら、備品管理にかかる時間のうち、大部分は「ラベルを探して確認」し「台帳に入力」する作業に費やされているからです。備品は頻繁に出し入れするものが多いため、誰でも一瞬で台帳への情報入力を済ませられるようになれば、作業にかかる時間は大幅に短縮できます。
この事実を踏まえ、私たちネットレックスでは、“ラベルをスキャンするだけで備品管理ができる” クラウド管理システム「Convi.BASE(コンビベース)」を開発・提供しています。
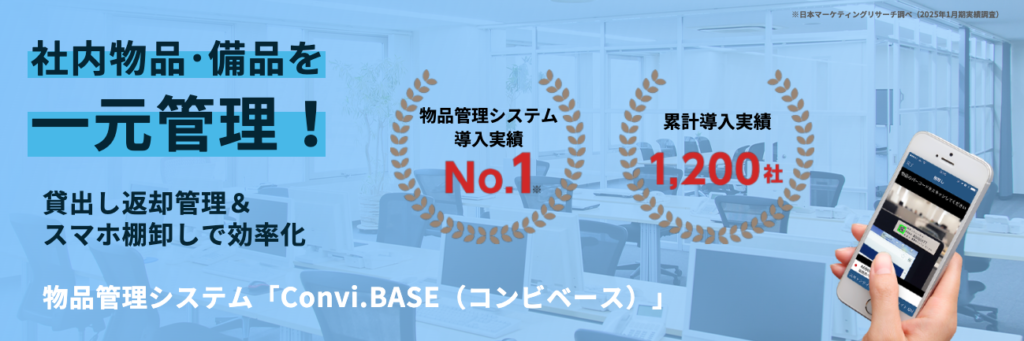
》》》導入企業1,200社を突破! 備品管理システムConvi.BASE(コンビベース)の詳細はこちら《《《
Convi.BASE(コンビベース)は、ブラウザからアクセスできるクラウド台帳と、QRコード・ICタグなどを搭載したデジタル管理ラベル、ハンディターミナルまたはスマートフォンアプリにより、「スキャンするだけ」で備品管理ができる管理システムです。
台帳は自由にカスタマイズ可能かつ複数作成できるので、備品だけでなく、固定資産やIT資産、リース資産、在庫、文書、鍵、工具、消耗品など、ありとあらゆる “モノ” をデータ化して一元管理することができます。
入出庫管理、数量管理、貸出し・返却管理、棚卸し、アラートメール機能、スケジューリング機能など、さまざまな機能を備えているのも特徴です。
使い方や機能・料金などについて詳しく知りたいという人は、下記ページをチェックしてみてください。
》》》備品管理システムConvi.BASE(コンビベース)の機能・料金・導入事例を見てみる《《《
備品管理に使えるアプリの利用
スマートフォンは、誰もが肌身離さず持ち歩いているデバイスです。そんなスマートフォンで、貸出し・返却や入出庫、保管場所の変更、棚卸しなどの管理ができれば、備品管理はさらに手軽になると思いませんか。
実際、QRコード・ICタグなどのデジタル情報タグとスマホのスキャン機能により、それを実現できるアプリが存在します。リモートワークの広がりにともない、近年、特に注目を集めるようになっています。
下記記事では、そんな「備品管理に使えるアプリ」について詳しく紹介しています。
「貸出し・返却」「入出庫」「数量管理」「棚卸し」などの管理をスマホから行えるようにしたい、という人は、ぜひチェックしてみてください。
無料プレゼント・資料ダウンロード
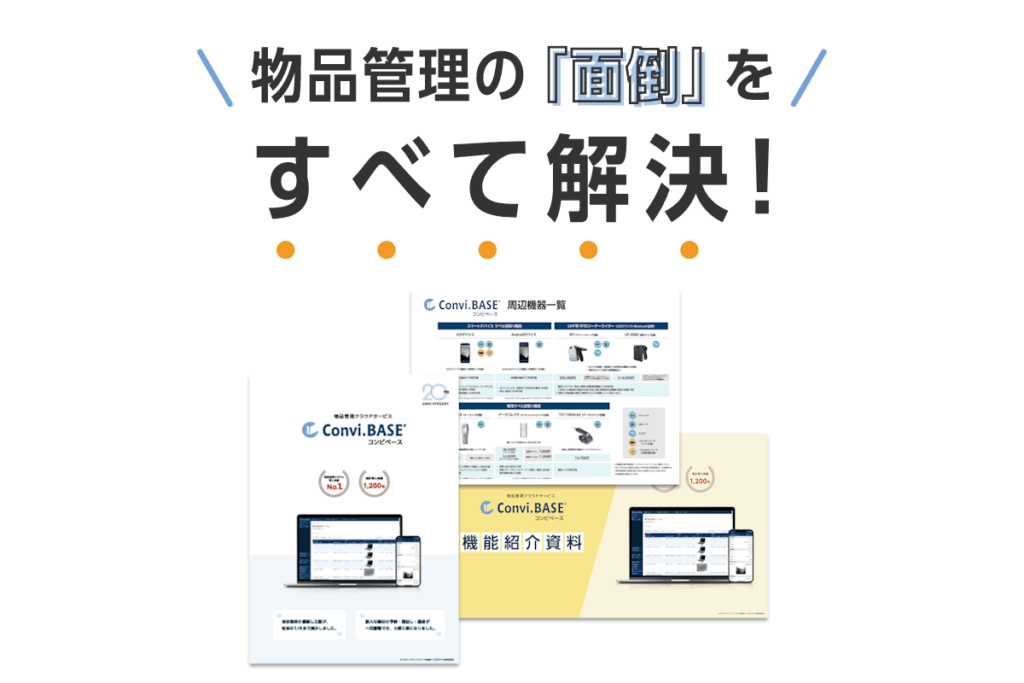
コンビベースのすべての機能や、導入事例、導入効果を知りたい方向けに、ご案内資料を無料でお配りしております。
- 「自社と同じ業種・規模の事例を読みたい」
- 「デモンストレーションで使い方をもっと知りたい」
- 「想定している運用が可能かどうか知りたい」
- 「使用中のシステムとの連携可否をチェックしたい」
- 「今すぐ見積もってほしい」
任意の「ご質問・ご要望」欄に、例のようにご入力いただきましたら、担当者が必要な情報を収集しまして後日お知らせいたします。
ぜひお気軽に、物品管理のお悩み解決にご利用ください。





