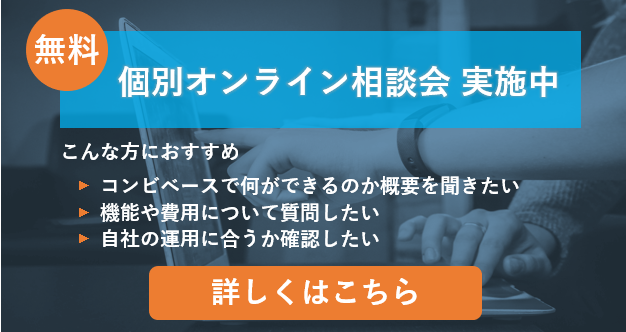物品管理を効率よく行うための有効な方法のひとつが「物品管理システムの導入」です。システムを導入することで、「物品情報の共有が簡単にできる」「棚卸しの工数削減ができる」などのメリットがあります。しかしこれはシステムをきちんと運用することで初めて得られるメリットです。 そこで今回の記事では、物品管理システムをスムーズに運用するための3つの事前準備をご紹介します。
システムを導入することで減る作業・増える作業
物品管理システムをスムーズに運用するためには「現在の管理工数がどのくらい削減できるのか」という点だけでなく、「システム導入によって新たに発生する作業」または「これまでと異なる作業」がどのくらい発生するのか?についても考える必要があります。
例えば、物品管理システムを導入することで
- 物品情報共有のための台帳整備、印刷、配布の手間
- 棚卸し(現物確認)のための準備、照合、集計作業
などの工数を削減することができます。
一方で、物品管理システムを導入した後には
- システムへの物品情報の登録
(これまでと異なる作業:Excelや紙の台帳に記入 → クラウド台帳への登録作業に変わる) - 管理ラベルの発行・貼付作業
(システム導入によって新たに発生する作業)
などの作業が発生します。
これらの作業をどの部署が、どのように行うのかなどの業務フローを明確にし、事前に準備をしておかないと、「システムを導入したけど活用されていない」ということにもなりかねません。 それでは具体的にどのような事前準備をしておけば良いのでしょうか?次の項で3つの事前作業をご紹介します。
物品管理システム運用前の3つの事前作業
≪マニュアル・業務フローを作る≫
システムを含めた物品管理業務のマニュアルを作成しましょう。
物品管理では購入~廃棄までのライフサイクルの中で「システムへの物品情報の登録」「管理ラベルの発行」「ステータス管理」などの作業が発生します。これらの作業を誰がどのように行うのかを明確にしましょう。
また運用がスタートした後も、マニュアルに沿ってきちんとシステムが運用されているかを定期的に確認するとより良い管理を実現できます。
≪社内説明会を開催する≫
物品管理に関わる担当者に参加してもらい社内説明会を開催しましょう。
実際にシステムを利用する担当者の疑問や不安を解消することができ、システム運用がスムーズになります。また単にシステムの操作説明を行うというだけでなく、システム導入の目的や現状の課題を共有する良い機会にもなります。物品管理への意識を高めるという意味でも、ぜひ社内説明会を設定しましょう。
≪システム運用の責任者を決める≫
システムに関する疑問点・運用に関する要望を取りまとめる責任者を決めましょう。
システム利用者から上がってきた疑問・要望を組織全体にフィードバックすることができ、管理業務の改善につなげていくことができます。また社内問い合わせ先を明確にすることで何かトラブルがあった時にもスムーズに対応できます。
無料プレゼント・資料ダウンロード

コンビベースのすべての機能や、導入事例、導入効果を知りたい方向けに、ご案内資料を無料でお配りしております。
- 「自社と同じ業種・規模の事例を読みたい」
- 「デモンストレーションで使い方をもっと知りたい」
- 「想定している運用が可能かどうか知りたい」
- 「使用中のシステムとの連携可否をチェックしたい」
- 「今すぐ見積もってほしい」
任意の「ご質問・ご要望」欄に、例のようにご入力いただきましたら、担当者が必要な情報を収集しまして後日お知らせいたします。
ぜひお気軽に、物品管理のお悩み解決にご利用ください。