多くの企業で導入が進み活用されているリース資産。この記事では、意外と知られていないリース資産の種類やメリット・デメリットについてご紹介します。
リース資産とは
リース資産とは、リース契約に基づいて導入した資産のことです。リース契約とは、機械や設備を購入するのではなく契約会社に代金を支払って長期間借りることを指します。
企業において最も導入されているリース資産は、パソコンや複合機などのOA機器ではないでしょうか。その他に工事用大型機械などもリース契約で導入されることがあるようです。
次に、リース契約にはどのような取引形態があるのか見てみましょう。
リースは、「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」の2つに分けられます。ファイナンス・リースは、さらに「所有権移転ファイナンス・リース」と「所有権移転外ファイナンス・リース」に分けられます。
リース契約が満了した時、リース資産の所有権が借り手に移る取引を「所有権移転ファイナンス・リース」、リース契約終了後も、リース資産が自分の所有物にはならない取引を「所有権移転外ファイナンス・リース」と定義されます。
<ファイナンスリース>
ファイナンスリースには、以下のような特徴があります。
- 中途解約ができない
ファイナンス・リースは、貸出期間の途中で契約を解除できません。長期間のリース契約を結んだ後に、気が変わって「解約したい」と思っても契約を途中で解除できないので注意しましょう。
- フルペイアウト
リース会社がリース期間中に設備を貸し出すために支払ったほぼ全額(設備等の取得価額、資金コスト、固定資産税、保険料など)を、借りる側が支払う義務があります。
ファイナンス・リースの会計処理では、所有権移転・所有権移転外に関わらず、資産を購入した時と同様の売買処理を行います。ただし、中小企業の場合には賃貸借処理が可能な場合もあります。
<オペレーティングリース>
ファイナンスリース以外のものがオペレーティングリースに該当します。
オペレーティングリースには、以下のような特徴があります。
- ファイナンスリースと比べて短い期間でリース契約をすることができる
借りる側の計画に合わせて柔軟にリース期間を設定できます。
- 費用を抑えられる
リース会社が支払った金額の全額を負担しなくてもよいので、ファイナンスリースと比べて金銭的な負担が少なくなります。重機のような高額な設備は、オペレーティングリースによる導入が適しているようです。
オペレーティング・リースの場合は、通常の賃貸借取引と同じように会計処理を行います。
リースのメリット・デメリットとは
業務に必要な設備をリース契約で導入すると、どのようなメリットとデメリットが生じるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
<リースの主なメリット>
- わずかなリース料で機械設備を導入できる
一般的に機械設備を導入しようとすると、多額な初期費用が必要となります。しかし、リースであれば月々わずかなリース料で設備導入が可能に。まとまった現金が一度に出ていかないので、手持ちの余裕資金を運転資金にまわすことができます。
- 設備の陳腐化を軽減できる
機械設備を購入すると、ある程度償却が進むまでは新しい機種に替えにくくなります。一方、リース契約で設備を導入し、耐用年数に合わせたリース期間を設定すれば、新しい機械設備への入れ替えが容易になります。
- リース料を経費として扱える
購入した場合は、減価償却の分のみが損金になるので、購入代金を支払っているにも関わらず全額経費にはできません。一方、リース契約で設備を導入した場合は、毎月のリース料を全額会社の経費扱いにすることができます。また、月額料金が固定されているのでランニングコストを把握しやすいこともメリットとなります。
<リースの主なデメリット>
- 中途解約ができない場合がある
ファイナンス・リースの場合は、税法上リース期間中に中途解約ができないので注意しましょう。解約を希望する場合は、残債を一括で支払って強制的に契約満了する必要があります。
- 所有権がない
リースしている設備機械の所有権はリース会社にあります。リース期間が終了した後も、リースしている設備機械の使用を希望する場合は再リース料が発生します。
- 支払い総額が割高になりやすい
リース料には、リース会社の手数料・保険料・金利・税金などが含まれるので、支払い総額が割高になることがあります。
リース資産、税制改正で変わった点は?
平成19年の税制改正により、平成20年4月1日以降に締結するリース取引は、売買取引として取り扱われるようになりました。改正後はリース期間定額法に従い、まずは資産を取得し、取得した資産を減価償却で経費とする、2つの段階で処理を行うようになりました。
資産を取得した場合や所有権移転ファイナンス・リースは、減価償却計算で経費化する(定率法)ので、取得時期に近いほど、経費計上額を大きく計上できます。一方、所有権移転外ファイナンス・リースの場合は、リース期間で同額を費用計上(リース期間定額法)するため、取得時からリース終了時まで、一定額が経費化されます。
リース資産の適切な管理方法とは?
次は、リース資産の管理方法についてご紹介します。
リース資産には、資産名称や使用部署などの情報を記した管理ラベルを貼付し、ひと目で情報を把握できるようにしておきましょう。
また、リース資産管理台帳を作成し、資産名称、使用部署、リース契約番号、リース物件番号、再リース番号などを記載しておくと、契約と資産を確実に紐づけることができます。他にも、「リース終了日」と「リース会社への更新回答期日」を記載しておき、リース契約が満了する前に、余裕を持って再リースの検討ができるよう期日管理しておくと便利です。
リース契約書の管理方法は、「契約を行った部署が管理する」「法務部など、1つの部署が全ての契約書を一括管理する」など、企業によってさまざまな方法が採用されています。社内ルールに従ってリース契約書を管理し、紛失を防止しましょう。
知っておきたい、リース資産にありがちなトラブル
管理を怠ると、自社で購入するより高くついてしまうこともあるリース資産。この章ではリース資産運用時に起こりがちなトラブルについて紹介します。
- 契約確認漏れにより、使っていない資産のリース費を支払ってしまっている
リース期限管理を怠ると、契約終了予定の物品の把握が漏れてしまう可能性があります。その結果「まったく使われていないパソコンに、リース費用を支払い続けていた」等の思わぬ損失が発生することがあります。
- 間違って転売・廃棄してしまった
リース資産が多くなると、自社が所有している資産とリース資産を区別できなくなることもあり、間違って第三者に転売、あるいは廃棄してしまう可能性があります。もし、契約期間が残っているリース物件を廃棄してしまった場合、リース中途解約金と損害賠償金をリース会社に支払うことになります。
- リース費用の管理に手間がかかる
リース資産の期限管理や、各部署への再契約の可否確認など何かと運用負荷が大きいリース資産管理。リース費用の管理と物品管理を別々に行っている場合は、管理に手間がかかるため、データ反映漏れが発生する可能性があります。
こうしたリース資産に関するトラブルや損失を防ぐためには、リース資産の把握・管理が必須です。リースのメリットを最大限享受するために、リース資産管理の方法を見直してみましょう。
無料プレゼント・資料ダウンロード
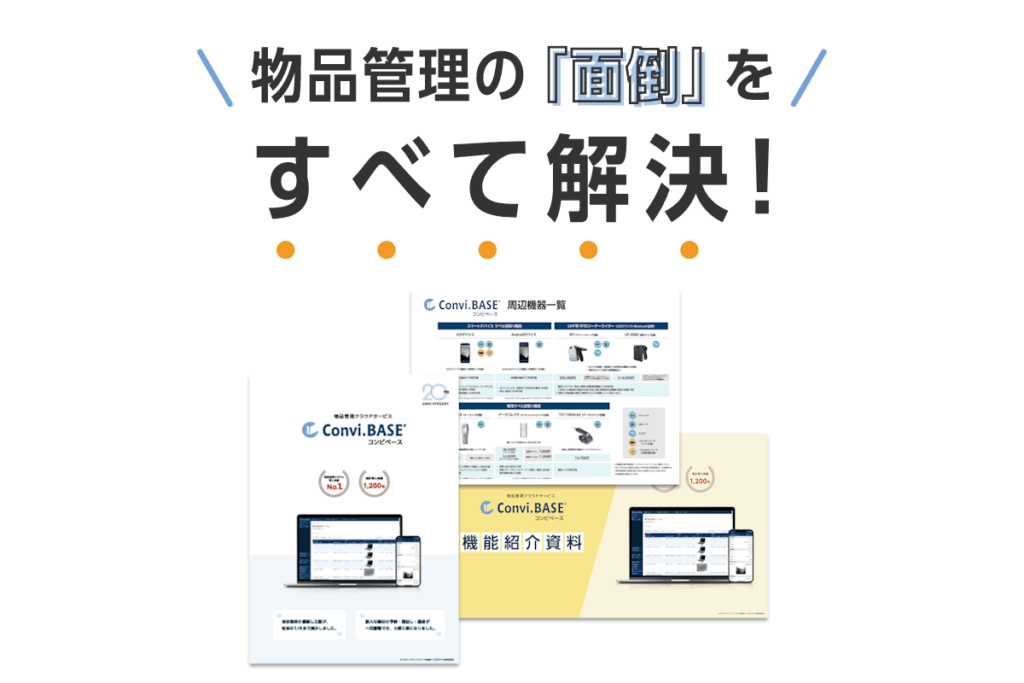
コンビベースのすべての機能や、導入事例、導入効果を知りたい方向けに、ご案内資料を無料でお配りしております。
- 「自社と同じ業種・規模の事例を読みたい」
- 「デモンストレーションで使い方をもっと知りたい」
- 「想定している運用が可能かどうか知りたい」
- 「使用中のシステムとの連携可否をチェックしたい」
- 「今すぐ見積もってほしい」
任意の「ご質問・ご要望」欄に、例のようにご入力いただきましたら、担当者が必要な情報を収集しまして後日お知らせいたします。
ぜひお気軽に、物品管理のお悩み解決にご利用ください。
このブログが皆様の「モノの管理のヒント」になれば幸いです。



